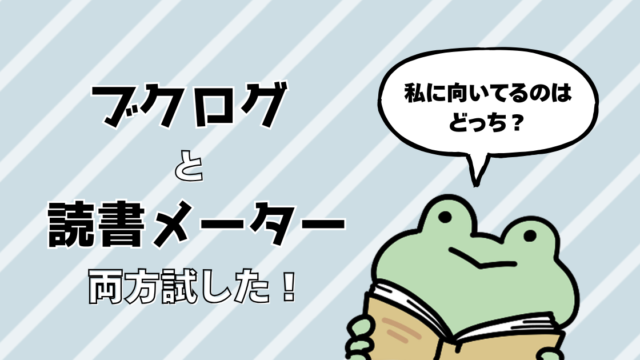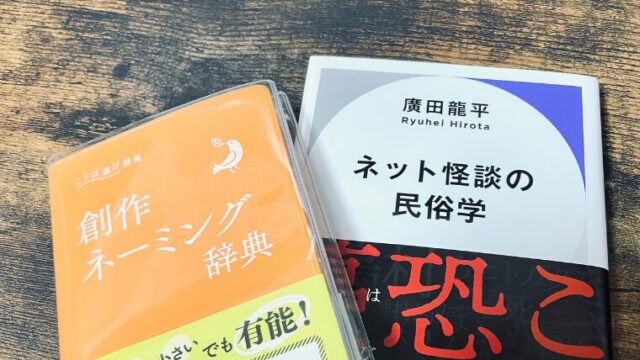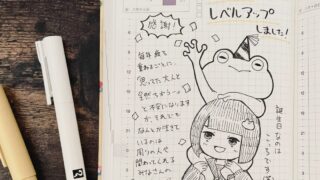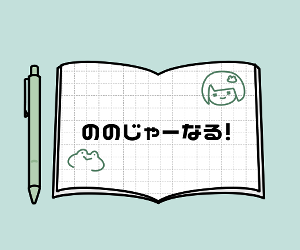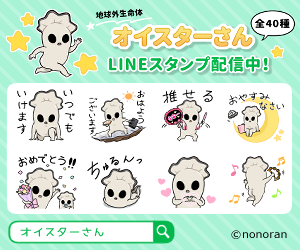【読書】今さらながら9月に読んだ本。人生哲学と歴史から学ぶ夏の終わり。
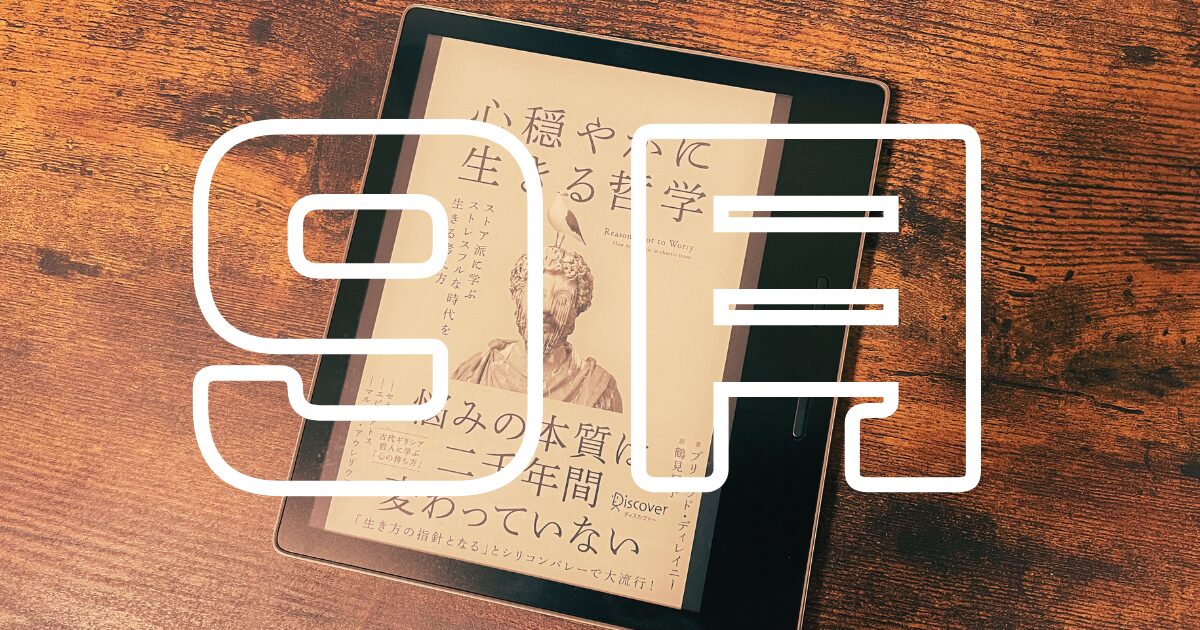
先月読んだ本から印象に残った本を紹介しよう!の回を毎月恒例にしたい。
こんにちは、管理人の野々蘭(ののらん)です。
おかしいな…ちょっと前に10月に入り誕生日だなんだと言っていたら、気付けばもう10月も折り返し地点を過ぎていました。
深呼吸している間に今年も終わりそうで怖いです。
そんなわけで、めっちゃ今さらな気もするのですが、今回も先月読んだ本の中から、とくに印象に残った本をご紹介したいと思います。
余談ですが、今回紹介する本は全部電子書籍で読んでました。
心穏やかに生きる哲学 ストア派に学ぶストレスフルな時代を生きる考え方/ブリジット・ディレイニー
ストア哲学は、紀元前3世紀初頭(今からおよそ2300年ほど前)に古代ギリシアで創始された哲学です。
そんな大昔に生まれた教えですが、情報過多で変化が激しく、多くの人がストレスや不安を抱える現代社会においても有効であると、今欧米やシリコンバレーを中心に再び注目されているといいます。
本書はストア派後期の賢人、マルクス・アウレリウス、エピクテトス、セネカらの教えを中心に、ストア哲学を生活のなかで実践した著者が、彼らの哲学のエッセンスや自身の経験談を語る本になっています。
なかでも何度も出てくる考え方が、『自分がコントロールできることとできないことを区別し、コントロールできることに集中する』ということ。
たとえば、他人の気持ちや行動だったり、病気や死、天候などは自分でコントロールできませんよね。
なのに、私たちはついコントロールできないことに対して心が乱され、時間もエネルギーも費やしてしまう。
そこで何か問題や苦しみにぶち当たったとき、「これは自分でコントロールできることか?」と考える習慣を持つだけでも、冷静に対処できるようになるはずです(そうは言っても、一朝一夕で習慣化できることではないかもしれませんが…)。
同様のことは現代の様々な自己啓発本にも出てきますが、2000年も前から言われていたというのには驚きますね。
ほかにも、「あれ?この時代ってSNSあったっけ?」と思うほど、現代社会に生きる我々がそのまま取り入れられそうな教えがたくさん出てくるので、目の前のことで心が落ち着かない日々を送る人には、いいヒントをくれる一冊だと思います。
“座右の銘言”になりそうな言葉がたくさん。
個人的に海外の本の翻訳本には少し苦手意識がありましたが、この本はとても読みやすく感じました(400ページ超えでちょっとボリュームはありますが。)
いわゆるビジネス書ではなく、著者がコラムニストであることも関係しているのかもしれません。
コロナ禍で、日本より厳しいロックダウン生活を強いられたストレスや経験も多く語られており、まるで海外の友人の話を聞いているような、そんな親しみやすさもありました(例として友人や同僚のエピソードがやたら出てくるの、海外の陽キャ寄り著者あるあるな気がする)。
ちなみに私もヘビーユーズしている、Amazonの「Kindle Unlimited」の読み放題対象になっています!(※投稿時)
人生にコンセプトを/澤田智洋
正解がなく選択肢が多い時代を生きるうえで、自分にとっての拠りどころとなる、「ライフコンセプト(人生を支える道としてのコンセプト)」を持とう!という本。
もともと「コンセプト」という概念?に対して強い興味関心を持っていたこともあり、楽しく読めました。
「そもそもコンセプトって?」、「良いコンセプトとそうでないコンセプトのちがいは?」、「どうやってつくるの?」という基本的なところも説明されていて、ビジネスや創作活動でのコンセプトづくりや、コピーライティングに興味がある人にも分かりやすく学びがある本だと思います。
面白いなと思ったのは、日々生活しているなかで感じる「モヤモヤ」がコンセプトにつながるということ。
「モヤモヤ」や怒りって、しんどいし疲れますよね。
だからついつい気付かないフリをして流したり、「こんなことを気にしている私が悪いんだ」と自責思考に陥ったり、できることなら無いほうがいい嫌なものだと思ってしまいます。
しかし著者は、「モヤモヤ」や「自分が世の中からズレている(浮いている)」という一見ネガティブに感じることこそ、自分を支えてくれるライフコンセプトをつくるヒントになると言います。
そう考えると、ネガティブな感情も無駄ではないと思えて、ちょっと前向きになれるのではないでしょうか。
もちろん詳しいコンセプトのつくり方や、「モヤモヤの分類(なるほど~とスッキリしました)」なども載っているので、是非手にとって、自分だけのコンセプトを考えてみてください!
コピーライターさんが書いているだけあり、キャッチーで印象的な言葉がたくさん出てくるのも面白いです!
ちなみに著者の澤田さんは、100個以上のライフコンセプトを持っているそう(もちろん、無理してたくさん作らなくても大丈夫です)。
たのしいプロパガンダ/辻田真佐憲
最近、日本史・世界史問わず歴史系の本や、社会学系の本にも興味を持っています。
辻田さんは、今年発売された『「あの戦争」は何だったのか』(講談社現代新書)が10万部突破のベストセラーとなっている、評論家・近現代史研究者の方です。
▲話題になり過ぎて、一時期Amazonや書店でも在庫が消えていた…(現在は復活)。
難しいイメージがある歴史系の新書でしたが、歴史に詳しくない人や、なるべくフラットな目線で戦争や近現代史を学びたいという人が手にとるのにちょうど良い本。
著者ご本人が様々なメディア(動画)で本書について語っているので、それらを見てから読むと、より本を書いた背景や伝えたいことが分かりやすくなると思います(私もそれで興味を持ちました)。
さて、そんな辻田さんの他の本も読んでみようかと思ったときに、表紙のインパクトがすごくて(笑)つい選んでしまったのが、この『たのしいプロパガンダ』です。
まず「プロパガンダ」という言葉については、本書の「はじめに」でこのように書かれています。
プロパガンダとは、「政治的な意図に基づき、相手の思考や行動に(しばしば相手の意向を尊重せずして)影響を与えようとする組織的な宣伝活動」のことである。
言葉自体を単純に訳すと「宣伝」という意味に過ぎないのですが、一般的には、政治的意図や特定の思想へ大衆を扇動するための宣伝活動、という意味で使われている言葉だそう。
そして本書は、プロパガンダ=上から無理やり押し付けられる退屈なものというイメージがあるが、多くは大衆が自発的に協力したくなるよう、「たのしい」ものとして行われていたという点に注目しています。
映画、音楽、アニメ、演劇…などなど、国や時代は違えど、プロパガンダは様々な娯楽の形で届られていたということは、教養として知っておいていいことなのではないかと思いました。
エンタメ的な話題や現代に近い話題も多いため、個人的には『あの戦』よりさらに読みやすく感じました。
また、「歴史の話」という過去のこととして捉えるのではなく、現代においても情報や娯楽の取捨選択は注意深くあるべき、という示唆も与えてくれます(あまり過敏になりすぎるのも、それはそれで好ましくない…ということにも最後触れていましたが)。
少し前から個人的に新書ブームがきているので(三宅香帆さんのYouTubeの影響を大いに受けている(笑))、今後も気になった本は、ジャンル問わずどんどん読んでみようと思います!
そんなわけで、9月に読んだ本の紹介でした。
最近は本当に読みたい本がたくさんあって、お金と体が足りません…(笑)
ここのところ哲学や歴史系がつづいているので、そろそろ全然毛色がちがう本も読みたいですね。
THE・サブカル!文学!お耽美!みたいなのとか(?)。
マジで小説を読まなすぎて、さすがに年内に一冊くらいは読みたいけど、最早やなにを選んだらいいのか分からなくなってきています…。
それでは、本日もお付き合いいただきありがとうございました!
¡Nos vemos!(またね!)