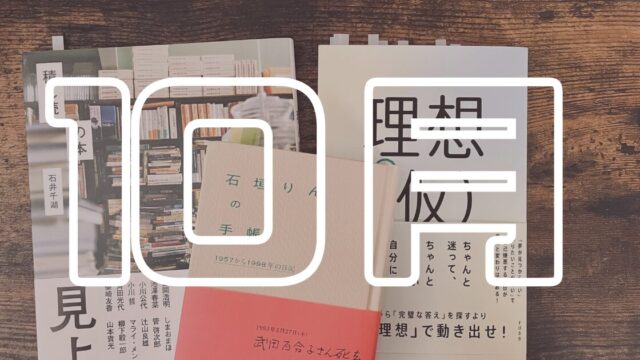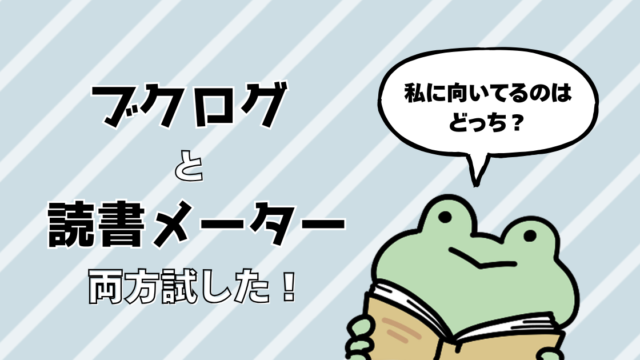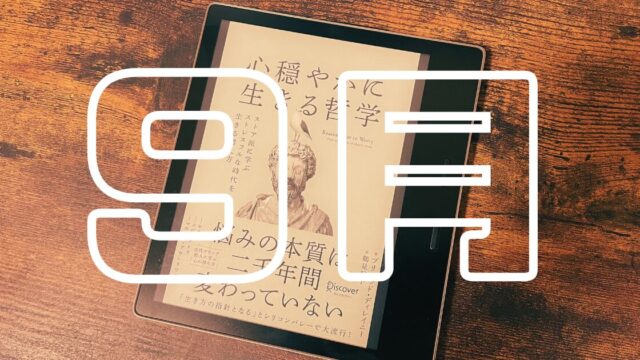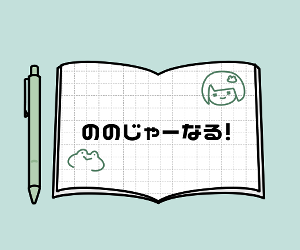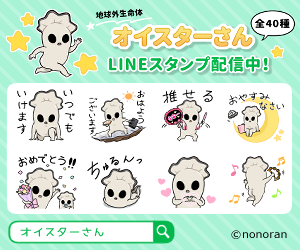【読書】「デジタルデトックス」を語りながら“ネット”怪談を学ぶ矛盾だらけの読了本紹介。
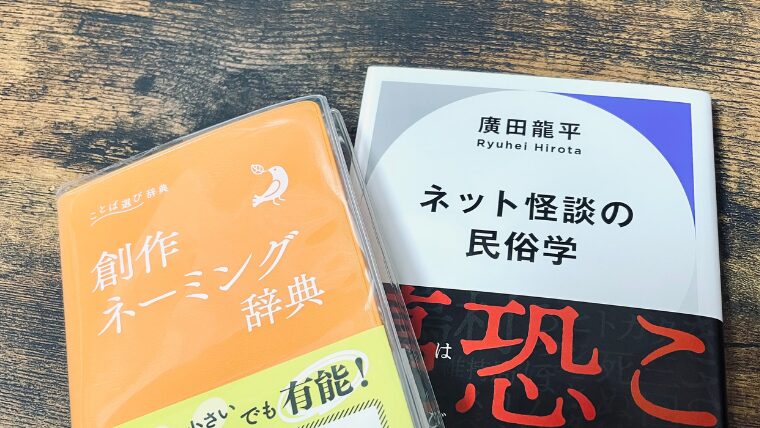
最近、読書が習慣化しつつあっていい感じです。
微妙な時間が空いたときや、画面を見すぎて疲れているときなどに、「とりあえず本でも読み進めるか~」というノリで気軽に本を読むようになりました。
便利でコスパが良いのは電子書籍ですが(Kndle Unlimitedなど)、こういうちょっとした休憩やすき間にさっと開けるという意味で、あらためて紙の本の良さを実感している今日この頃です。
ちなみに8月は、手帳の公式ガイドブックや雑誌を含めると9冊読みました。
手帳関連の本については、別館で語ったりしているので、よければそちらもご覧ください。
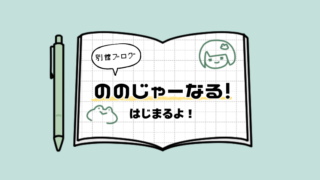
そんなわけで、先月読んだ本の中から、とくに印象に残った本を3冊ほどご紹介します!
戦略的暇―人生を変える「新しい休み方」/森下彰大
「デジタルデトックス(スマホやPCなどのデジタル機器から一定期距離をとること)」に関心があり、今年に入ってから関連しそうな本を何冊か読んでいます。
脳科学、哲学の視点から書かれた本もあれば、SNSメインの仕事をしていた人が、SNSで常に人とつながる生活を手放した体験談など…。
いろんな本がありましたが、その“総ざらい”的な本になっていて、最近デジタルデトックスに興味を持った・必要性を感じているという人がまず読んでみるのにオススメな一冊です。
今の社会はどういう状況になっていて、私たちはどんな問題を抱えているのか、というのを丁寧に見ながら、テクノロジーとは切っても切り離せない生活の中で、なにを心がけていくのかを考えていきます。
はっとさせられたのは、便利な環境やインターネット、コスパ・タイパを求める風潮に慣れ過ぎたことで、「すぐに結果が出る」、「すぐになにかを得られる」という即時性を求めてしまうようになったという話。
逆を言えば(私自身)、「結果が出るまで粘る」、「ゆっくり待つ」、「答えが分からないままでいる」ことにどんどん耐えられなくなってきているなぁと…。
Amazonで注文すれば翌日には届くし、ネットでなにかを発信すれば(ある程度人目のあるアカウントなら)すぐにリアクションが付くし、ソシャゲのガチャはその場で結果が出るし、分からないことはとりあえずAIに聞けば答えてもらえます。
それはたしかに便利だったり楽しかったりするけど、逆にそうじゃない状況になったとき、余計な焦りやイライラに襲われて、むしろ生きづらくなっている気すらするかも…(便利さを知る前の時代は、それが当たり前だったのに)。
もちろんテクノロジーやネットコンテンツ、SNSを悪だと言いたいわけではないし、そう単純な話ではありません。
現に私たちは、たくさんの技術の進歩の恩恵を受けて生活しています。
ただ、情報過多に対する疲れや漠然とした不安、自分の時間の使い方はこれでいいのだろうか?ということが頭をよぎったときに、こういった本からヒントを得てみるのもいいんじゃないかなと思います。
この本は、時間を置いてまた読み返したいです!
ネット怪談の民俗学/廣田龍平
全く知らなかったけど、本屋さんでたまたま手に取り気になって買った本です(笑)
先に言っておきますが、私はホラーや怪談が苦手です。
じゃあこんな本買うなよと思われそうですが、民俗学という視点から「ネット怪談はどのように広がっていったか」、「(創作ホラーや口伝とはちがう)ネット怪談としての特徴」などを冷静に分析していくのであれば、あまり怖くないのかなと思ったんですよね。
あと、これは感覚でしか説明できないんですが、ホラーや怪談は苦手だけど、「不気味な雰囲気」や「世界観が魅力的なもの」は好きです(本書で取り上げられている「リミナルスペース」とか、舞台やキャラが魅力的なホラーゲームの世界観とか)。
予想どおり、怪談そのものをおどろおどろしく書いてはおらず(とても淡々としている)、眠れないほど怖い!ということはありませんでした(「ジェフザキラー」の画像をいきなり出されたのだけは心臓に悪かったけど 笑)。
逆を言えば、有名なネット怪談はたくさん挙がっているものの、一つ一つを詳細に解説してはいないので、怪談そのもののストーリーは知っている前提(あるいは各自調べてね)って感じです。
私はどれもふわっと聞いたことがある程度なので、ちゃんと知っているネット怪談ファンが読めば、「あの話ってここが初出なんだ!」「話題になったあとこんなことが判明してたの!?」とか、もっと楽しめたのかもしれません。
個人的には、一種のネット史として面白いなぁと思いました。
個人サイトの時代から掲示板の時代、SNSの普及、そして誰でも動画投稿やライブ配信が可能に…と、どんどん時代が移り変わっていく中で、「怖さ」の楽しみ方も変わってきているんですね。
テクノロジーが進化してく一方で、逆に今はアナログホラー(デジタル映像が主流になる以前に撮られたもの、といった設定のノイズがかった古い映像で表現されるホラー作品など)が人気というのも興味深いです。
ファッションやキャラクターグッズなどでもレトロなもの、懐かしさのあるものが流行っているけど、そこも関係あるんでしょうか…?
ホラーゲームでも、「発見したVHSを見てみると、今いる場所で怖いことが起きている映像が…」とかよくあるよね。
創作ネーミング辞典/学研辞典編集部
以前ブックオフ購入品で紹介した、『感情ことば選び辞典』と同シリーズの辞典。
気になっていたので、こちらも購入してみました!

創作クラスタ向けの辞典シリーズということで、タイトルや技名(笑)などに困ったときの参考として、約1000語のキーワードを8ヵ国語で紹介しています。
どういった感じで書かれているかは是非Amazonなどのサンプルを見ていただきたいのですが、マジで眺めているだけでも楽しいです。
もともと語学に興味があったのもありますが、同じ言葉を一気に8ヵ国語で見られるのは普通に勉強にもなるし面白いです(いろいろな言葉の語源になっているラテン語が入っているのがまた嬉しい)。
ファンタジー系の創作でなくても、架空のブランド名とか、曲名とか、使いどころはいろいろありそうなので、今後ちょこちょこお世話になろうかなと思います!
ちなみに完全に余談ですが、ブログに貼ろうとして調べていたら、まさかのツイステコラボ版があったことを知りました(笑)
ぶっちゃけ私はツイステ序盤で止まってしまった超絶にわかなのであまり語れませんが、どうやらほかの辞典も各寮とコラボしているようです。
ていうか、自分が買った辞典のコラボが、初見で一番好みだったスカラビア(ジャミルくん)だったからびっくりしたよ…(笑)
どこまでもオタクを刺しにくる学研さん…!(笑)
それでは、本日もお付き合いいただきありがとうございました!
なんだか前半真面目だったのに、後半にいくにつれてただのオタクと化すカオスな本紹介になってしまいました(笑)
また気が向いたら、こうしてゆるい本紹介をしていきたいと思います。
¡Nos vemos!(またね!)